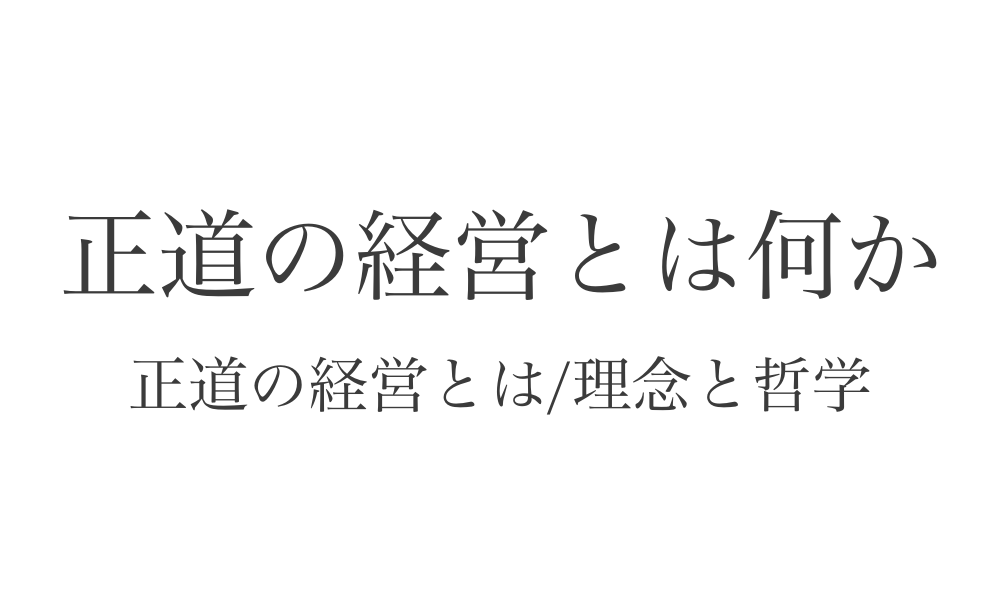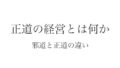経営には「速く」「大きく」「安く」を追い求める道と、「正しく」「長く」「深く」を追い求める道があります。前者はしばしば短期間で成果を出すことができますが、その裏側で無理や歪みが蓄積されます。一方、後者は時間がかかる分、積み重ねた信頼や組織の土台が揺らぎにくく、長期的に続く事業を築くことができます。私は後者を「正道の経営」と呼び、その理念を軸に事業を進めてきました。
正道の経営の定義
正道の経営とは、「利益よりも信頼を優先し、短期の成果よりも長期の持続性を選ぶ経営姿勢」です。
これは単に倫理的に正しいことをするという意味ではなく、経営資源の使い方と判断基準を、すべて長期視点で最適化するという考え方です。
正道を歩む経営では、急成長を求めるあまりスタッフを酷使したり、顧客の期待を裏切るような安易な値下げを行ったりしません。短期的な売上を捨ててでも、ブランドや人材、顧客との信頼関係を守る判断を優先します。
なぜ正道が選ばれにくいのか
現代は情報が瞬時に広がり、数字やランキングで比較される時代です。その中で「スピード」と「規模」は目に見える評価軸となります。
だからこそ、短期間で店舗数を増やし、売上を一気に伸ばす戦略が称賛されやすい。しかし、その影で人材不足や品質低下が進み、長期的には事業が縮小してしまう例も少なくありません。
正道は時間がかかるため、途中で成果が見えずに不安になる瞬間が必ず訪れます。そのため、経営者としての忍耐力と信念が試されます。
正道経営の3つの柱
- 人を育てる
- 即戦力の奪い合いではなく、自社で人を育てる文化をつくる。
- 教育はコストではなく投資であると考える。
- 顧客との長期関係
- 一度だけの取引ではなく、何年も利用してもらえる仕組みを構築する。
- 誇張した広告や短期的な値引きではなく、実際の価値で選ばれる。
- 無理のない成長
- キャッシュフローと人員配置のバランスを保つ。
- 拡大のタイミングは内部体制が整ってから。
実践による効果
私が正道の経営を実践してきた中で感じる最大の効果は、「人が辞めない」ことです。
人が辞めないから顧客の信頼が積み上がり、顧客が減らないから売上の土台が安定する。この循環は、広告や販促では得られない強さをもたらします。
まとめ
正道の経営は派手さこそありませんが、嵐が来ても倒れない経営基盤を築くための道です。
短期的な評価軸に揺らがず、理念を貫く姿勢こそが、10年後も事業を続けられる唯一の方法だと私は考えます。